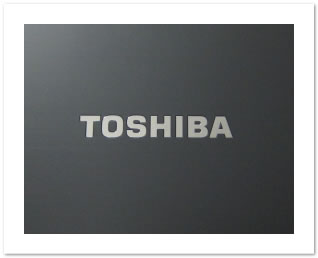続きを読む
東芝が過去の決算で利益を前倒し計上するなどの不適切な処理をしていた問題で、同社は22日、テレビ、パソコン、半導体の各事業でも不適切な処理があった可能性があると発表した。主力の半導体を含む幅広い事業で不適切処理が行われていた疑いが出てきた。
テレビ事業では販売促進のための費用を実際とは違う時期に計上していた疑いがあり、半導体事業では在庫の価値を不当に高く見積もっていた可能性があるという。パソコン事業では、製造を委託していた企業との間の取引で損失や利益を正しく計上していなかった可能性があるという。
東芝は電力、社会インフラ、ビル管理の3事業で利益の前倒し計上があったとして、15日に立ち上げた第三者委員会に調査を依頼している。新たに不正の疑いがわかった3事業についても追加で調査を依頼した。
http://www.asahi.com/articles/ASH5Q44G9H5QULFA00F.html
東芝、テレビ・パソコン・半導体事業でも不正会計の疑い
-
- カテゴリ:
- ニュース
-
- カテゴリ:
- ニュース
- タグ :
- #東芝
-
- カテゴリ:
- ニュース
-
- カテゴリ:
- ニュース
-
- カテゴリ:
- ニュース
- タグ :
- #東芝
-
- カテゴリ:
- ニュース
-
- カテゴリ:
- タブレット
0Comments
東芝の株がストップ安、安田秀樹アナリスト「(不適切な会計は)基本的に粉飾決算のことだ」と指摘
続きを読む
(ブルームバーグ):不適切な会計処理があったと発表した東芝 の株価は11日、値幅制限いっぱいのストップ安で取引を終えた。
東芝株は前週末比17%安の403.3円とストップ安(80円)で売買が成立し、そのまま取引終了となった。1日の下落率としては2011年3月以来となった。
東芝は8日、複数のインフラ工事の会計処理に不適切な点があったとして、社外の専門家で構成する第三者委員会を設置して調査すると発表。これに伴い前期(2015年3月期)の業績予想を取り消すとともに、期末は無配とした。
発表資料によると、これまでの調査で14年3月期以前の過年度決算を修正する可能性も生じている。決算発表は6月以降になる見込みで、株主総会の開催日も決まり次第公表する。
エース経済研究所の安田秀樹アナリストは、不適切な会計は「基本的に粉飾決算のことだ」と指摘。株価の前提となっていた業績に疑義が生じていることに加え、問題の損益への影響についての開示がないと批判した。
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NO5SWM6JTSE901.html
東芝、3次元メモリー「48層」実現で不良品率の高いサムスン32層をブチ抜き世界一に!
続きを読む
サムスン超え、東芝世界一へ 3次元メモリー「48層」年内量産
東芝がスマートフォンなどに使われる記憶用半導体の「3次元タイプ」のNAND型フラッシュメモリーで、韓国のサムスン電子を上回る製造技術を開発したことが24日、わかった。記憶素子を垂直に積載する3次元メモリーはサムスンが昨年から32層の積層品を量産しているが、東芝は48層のタイプを開発し世界一に躍り出る。東芝は今年後半から量産する計画で、今後、スマホなどに保存できるデータ容量が飛躍的に増える可能性がある。
東芝が開発する3次元メモリーは、従来タイプよりも記憶容量を大幅に高められ、半導体の小型化も可能で、次世代の競争を左右する技術とされる。
これまでは記憶素子を平面に並べ、回路線幅を縮めることで、容量を拡大する手法が主流だったが、微細化は限界に来ている。3次元メモリーは記憶素子を積むほど容量が大きくなる利点があるが、製造コストがかかるのが課題だ。
昨年から量産を開始しているサムスンも不良品率が高く、採算面で厳しいとの声もある。東芝も同様の課題を抱えていたが、生産技術のめどが立ち、サンプル出荷を決めた。メモリー容量は、サムスンよりも上回っているもようだ。
東芝は、今夏に一部の建て替えが竣工(しゅんこう)する四日市工場(三重県四日市市)で、新製品を量産する。
http://www.sankei.com/economy/news/150325/ecn1503250002-n1.html
東芝製ノートPCから出火、東芝に賠償命令。バッテリーはパナソニック製
続きを読む
東芝製のノートパソコンから出火したとして、神戸市東灘区の男性が同社に慰謝料など約960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁であり、吉田祈代裁判官は約80万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2011年12月、電源につないだ状態のノートパソコンをテーブルに置いたまま就寝。バッテリーパックが過熱発火して高温の部品が周辺に飛散し、床面や布団などを焼いた。 バッテリーパックはパナソニック製だった。
東芝側は、商品に欠陥があったことは認めていた。吉田裁判官は「本来出火の危険が想定されないもので、近くで寝ていた男性が一定の恐怖を感じたことは認められる」 として、男性の精神的苦痛に対する慰謝料の支払いも一部認めた。
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/0007850732.shtml
学生に5万円負担させ授業にタブレット導入した佐賀県、故障だらけで全く活用できずwwwそうArrowsならね
1: かかと落とし(岐阜県)@\(^o^)/ 2015/02/25(水) 13:59:56.61 ID:PUdf1cf60.net
夏以降は、ソフト関連ではなく、パソコン本体に多数のトラブルが起きたことを示している。使い込むうちに、機材(タブレット型パソコン「ARROWS Tab Q584/H」)の脆弱性が高まったと見られ、平成27年度は別の機種に変更されるという。 これでは何のために億単位の県費をかけ実証研究を行っていたのかわからない。無責任極まりない話である。
(略)
こうした状況をどう考えているか――佐賀県内の教育関係者に話を聞いてみた。
――「授業開始と同時にパソコンを立ち上げるよう指示したとしても、すぐに生徒全員のパソコンが揃うわけではない。動きが重かったり、故障であったり、電池が切れていたりとトラブルはつきもの。 パソコン自体を忘れてくる生徒もいる。結局、実質的に授業を始めるのは10分か、最悪な時は15分以上も後になる。そうなると邪魔なだけ。パソコンを使うたびに授業が遅れるのだから、そのうち『止めておこう』となる。 まじめにパソコンを使い続けないと申し訳ないというので、支障のない範囲でパソコンを使っているというのが実情。 ほとんど似たり寄ったりの状況ではないか」(県立校教員)
――「(パソコンは)眠らせておきたい。できれば使いたくない。実際、パソコンを敬遠する先生の方が多いのではないか。 インストールはできない、故障はする。なんでこの機種を選んだのか、聞いてみたい。実証研究したうえでウィンドウズを選んだらしいが、私は間違ってると思う。使い勝手が悪すぎる。教員の習熟度にも問題があって、積極的にパソコンを利用しようという先生と、そうでない先生との差があり過ぎる。一番の問題は、パソコンを利用したことで、成績が上がったかどうかの判定ができないこと。学校によって使う場面、回数がバラバラでは話にならない。
必要だったのは教員にパソコン授業に対する理解を求め、習熟する時間を与えることだった。小手先だけの研修ではダメ。宝の持ち腐れになってしまう。現状がまさにそれだ。この事業は、立ち止まって検証する必要がある」(県教委関係者)
http://hunter-investigate.jp/news/2015/02/23-saga-pc.html
http://hunter-investigate.jp/news/2015/02/24-saga-pc.html
続きを読む
東芝、Netflixに対応した2Kテレビ「REGZA J10」シリーズを発売
1: 1級神2種非限定φ ★ 2015/02/14(土) 07:47:53.01 ID:???.net
東芝ライフスタイルは2月12日、背面全体に高輝度LEDを配置した2K解像度の液晶テレビ「REGZA J10」シリーズを発表した。 2015年秋に日本でのサービスを開始する映像配信サービス「Netflix」に対応する。発売は2月20日。
J10シリーズは55V型「55J10」(想定税別価格:20万円前後)、49V型「49J10」(同:17万円前後)、43V型「43J10」(同:13万円前後)の3モデルをラインアップ。画面全体にLEDを配置した「全面直下LED」を採用し、高輝度かつ高コントラストな映像を再現する。
地上デジタルチューナ3基、BS、110度CSデジタルチューナ2基を搭載し、USB HDDを接続すれば、同時に2番組を録画できる「地デジ見ながらW録」や「タイムシフトマシン」対応の東芝製レコーダーをテレビのリモコンだけで操作できる「タイムシフトリンク」を搭載する。
YouTubeやTSUTAYA TVなどのネット動画サービスに加え、2015年秋に日本でサービスを開始するNetflixにも業界で初めて対応した。
4Kレグザのデザインコンセプトであるミニマルデザインを継承し、ブラックフレームとサテンゴールド色のリアルメタルスタンドを採用。スピーカシステムには「ラビリンスバスレフ型BOX」により、インビジブルスピーカながら、豊かな低域再生を実現する。
約0.05フレームの低遅延を誇る「瞬速ゲームダイレクト」により、ゲームプレイ時でもストレスの少ない使い勝手を提供。 「映像メニュー」が「ゲーム」の時、ゲームやゲーム機の種類ごとに映像モードを変更しなくても、適切な映像でゲームができる「オート」モードも備える。
http://japan.cnet.com/digital/av/35060383/
続きを読む
東芝の研究データをSKハイニックスに流出させた事件 元社員・杉田吉隆が認める
1: ちゃとら ★@\(^o^)/ 2015/01/21(水) 06:52:29.57 ID:???0.net
東芝の半導体の研究データを韓国の企業に漏らしたとして不正競争防止法違反の罪に問われた東芝の提携先企業の元社員に対する初公判が東京地方裁判所で開かれ、元社員は起訴内容を大筋で認めました。
東芝の提携先の元社員、杉田吉隆被告(53)は7年前、東芝が開発していた「フラッシュメモリー」という半導体に関する 研究データをコピーし、その後に転職した韓国の半導体大手「SKハイニックス」に提供したとして、不正競争防止法違反の罪に問われています。
20日、東京地方裁判所で初公判が開かれ、元社員は起訴された内容について、「おおむねそのとお りです」と述べ、大筋で認めました。
検察は冒頭陳述で、「被告は転職後の自分の扱いが有利になると考え、データをコピーした。東芝は他社に先駈けて開発を進めていたが、韓国企業へのデータ流出によって競争力の低下を余儀なくされた」と主張しました。
これに対し、弁護側は「データを持ち出したのは自分の知識を高めるのが目的だった。転職先に教えた情報は秘密性が高いものではなかった」と主張しました。今回の裁判では、企業の機密情報の内容が審理されるため、一部の証人尋問は非公開で行われることになっています。
この事件を巡っては、「SKハイニックス」が東芝に日本円で330億円余りを支払うことで、企業間の和解が成立しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150120/k10014816991000.html
続きを読む
東芝、スマホにかざすだけで中身を確認できるNFC搭載SDHCカードを発売
1: 夜更かしフクロウ ★ 2015/01/07(水) 23:33:41.68 ID:???.net
東芝セミコンダクター&ストレージは1月6日、世界初となるNFC(近距離無線通信)機能搭載のSDHCメモリカードを発表した。2月から順次販売する。
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1501/07/news127.html
続きを読む
東芝、NANDフラッシュの機密情報流出で韓国SK Hynixと和解。新たな協業についても合意
1: 鰹節山車 ★@\(^o^)/ 2014/12/19(金) 18:52:19.71 ID:???0.net
東芝、NANDフラッシュの機密情報流出でSK Hynixと和解
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20141219_681207.html?ref=rss
株式会社東芝は19日、2014年3月13日に提訴した、NANDフラッシュメモリに関する韓国SK Hynixに対する訴訟について、SK Hynixが東芝へ2億7,800万ドルの和解金を支払うことで合意したことを発表した。
この訴訟は、SK Hynixへ移籍したSanDisk日本法人の元従業員が機密情報を不正に持ち出したことによるもの。この元従業員は不正競争防止法違反の容疑で逮捕され、これを認めていた。
東芝はニュースリリースの中で、「当社は、事業競争力の源泉である技術先進性確保のため、不正競争行為に断固たる対処を進めてきましたが、交渉の結果、今般、SK ハイニックス社と和解の合意に達したものです」(原文ママ)と決定の理由を記している。
また、今回の和解を機に、東芝とSK Hynixは新たな協業関係を構築。DRAM供給契約、特許クロスライセンス契約期間の延長、次世代露光装置候補のナノインプリントリソグラフィ技術の共同開発について合意した。
関連
プレスリリース
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2014_12/pr_j1902.htm
韓国SKハイニックス社との訴訟における和解とメモリ事業における協業拡大について
当社は、NAND型フラッシュメモリの技術に関する機密情報について、韓国SKハイニックス社がこれを不正に取得・使用したとして、不正競争防止法に基づく損害賠償等を求める民事訴訟を本年3月13日に東京地裁に提起しましたが、本日、同社と和解に合意しました。本合意に基づき、当社はSKハイニックス社から和解金の支払いを受けます。
当社は、今後も事業競争力の源泉である技術の先進性を確保していくため、最善の情報漏洩防止体制の構築を図るとともに、不正競争行為に対しては断固たる措置を講じる方針です。
一方、当社とSKハイニックス社は、2011年から次世代メモリであるMRAMを共同で開発するなど従来から提携・取引関係にあります。
この和解を機に、両社は新たな協業関係の構築を目的に、DRAM供給契約及び、特許クロスライセンス契約期間の延長、次世代露光装置候補の一つであるナノインプリントリソグラフィ技術の共同開発について合意しました。これにより、当社のメモリ事業の更なる強化を図ります。
別紙: 韓国SKハイニックス社との訴訟における和解について[PDF: 135KB]
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2014_12/j1902/cover2.pdf
続きを読む